 奥の細道
奥の細道
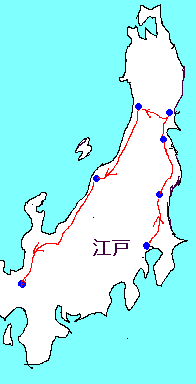 ご存知、松尾芭蕉が、江戸から発して、東北の南部を
ご存知、松尾芭蕉が、江戸から発して、東北の南部を
ぐるりと旅しながら、俳句を詠んだ有名な旅日記である。
日本文学の古典的名作と言われている。
全行程2400キロ、150日間に渡る紀行である。
「行く春や 鳥啼き(なき)魚の 目は泪(なみだ)」
「しづかさや 岩にしみいる 蝉(せみ)の声」
「夏草や 兵(つわもの)どもの 夢の跡」
「五月雨(さみだれ)の 降り残してや 光堂」
「荒波や 佐渡によこたう 天の河」
などは誰もが知る名句である。
それゆえに、東北の各地で、芭蕉が訪れた土地は、
観光の目玉となっていて、観光客を引きつけている。
それほどに有名な「奥の細道」であるが、実は、
その内容はかなり多くのフィクションを含んでいる。
例えば、岩沼に一泊したことになっているが、本当は
夕方にそそくさと駆け抜けているし、石巻についても、
道を間違えて、たまたま辿り着いてしまったように書いて
あるが、本当は、事前に調べて行っているのである。
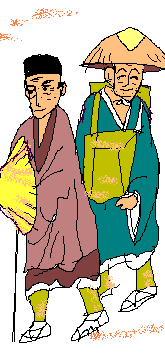 また、
また、
「五月雨を降り残してや…」の平泉は、当日は快晴だったし、
「佐渡によこたう天の河」を歌った越後の出雲崎では
滞在した二日間、ずっと、どしゃぶりであった。
など、事実とはずいぶん違っている。
それが判明したのは、比較的、新しく、昭和18年である。
その年、曾良(そら)の随行日記が初めて、公開されたのだ。
奥の細道の旅に、ただ一人随行した弟子の曾良は、実に
几帳面な男で、旅の内容を事細かに金銭的なことまで
書き残していたのである。
芭蕉の紀行文をそのまま信じていた学会は、大混乱したらしい。
まあ、それでも文学的な価値は変わらないということで、
収束した。
実は、芭蕉は、この「奥の細道」を後世に残るような
完璧な文学作品に仕立てようと意気込んでいたふしがある。
芭蕉は29才の時、徘諧師として名を上げるため、関西から
江戸へと出てきたのであるが、当時の俳句というのは、
風刺と諧謔を主とした、むしろ川柳に近いものだった。
俳諧師は、金持ちのパトロンや客に媚びる芸能人であり、
現在、考えられるような、文学の雰囲気はなかった。
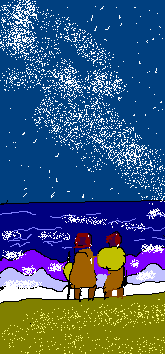 当初はそれに甘んじていた芭蕉だったが、やがて不満が募る。
当初はそれに甘んじていた芭蕉だったが、やがて不満が募る。
日本文学の古典である、古今和歌集などに触れるにつれ、
詩人としての魂に、火がついたらしい。やがて、
古典の風雅や、わび、さびを意識した、奥深い俳句を創作
するようになり、そういう新しい俳句の一派を作る。
その新しい蕉派の俳句の金字塔として、彼が考えたのが
「奥の細道」という文学作品としての紀行文である。
練りに練った完成品にしよう。ドラマチックにしようと思った。
既に46才。元々、虚弱体質であり、持病の痔や、胃弱が
いよいよひどくなっていたが、思い切って東北道を選んだ。
当時の東北道は未整備で、困難きわまる旅だったが、
芭蕉が心酔する平安時代の歌人・西行法師が歩いた道であり、
彼が歌に詠み込んだ歌枕が、あちこちにあった。
歌枕というのは、古典の歌に読み込まれた名所であり、
芭蕉は、その一つ一つを訪れては感動に浸った。
と言いたいところだが、実際は、平安時代の歌枕も
江戸時代になると、草に埋もれてわからないことが多く、
「白河の関」なども、それらしい碑を見つけて感動している。
仙台での歌枕の一つは、「宮城野原の萩の花」だが、
萩というのは秋に咲く花であって、芭蕉が行った夏には
葉っぱだけである。それでも、彼は宮城野原に立って、
萩の咲いた風景を想像して一生懸命、感激している。
要するに、「奥の細道」というのは、
実際に旅はしているものの、その半分は芭蕉の頭の中で
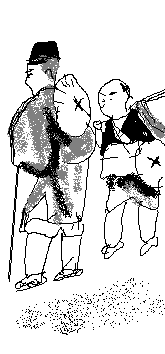 あらかじめ想像され、ドラマチックに仕立てられ、
あらかじめ想像され、ドラマチックに仕立てられ、
現実をねじ曲げてでも、感動的な一編の抒情詩にしよう
と企画された作品なのである。
ただ、それによって、文学作品としての価値が
落ちるわけではなく、日本文学史上、永遠の名作である。
ついでに、付け加えておけば、奥の細道の旅は
最北が岩手県・平泉だが、本当は芭蕉は津軽まで
行きたかったらしい。それを同行の曾良から
「そんな身体で行けますかいな」と言われて、
断念している。それで、日本海に行くが、
酒田でも、北に行きたいと駄々をこねて、
曾良と口喧嘩をしたらしい。結局、芭蕉が折れたが、
旅の終盤、石川県で二人はそっけなく別れている。
酷暑の長旅で、相当参っていたらしい。
 元にもどる
元にもどる
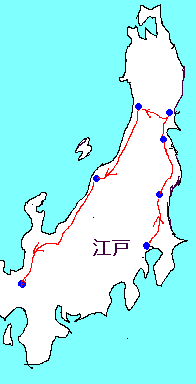 ご存知、松尾芭蕉が、江戸から発して、東北の南部を
ご存知、松尾芭蕉が、江戸から発して、東北の南部を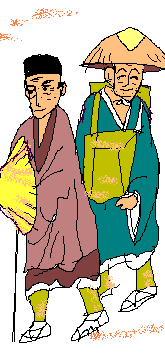 また、
また、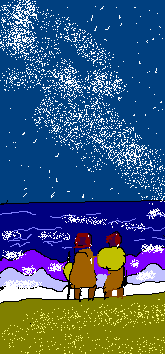 当初はそれに甘んじていた芭蕉だったが、やがて不満が募る。
当初はそれに甘んじていた芭蕉だったが、やがて不満が募る。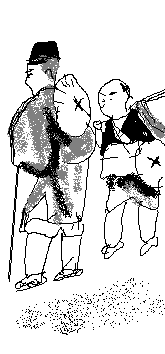 あらかじめ想像され、ドラマチックに仕立てられ、
あらかじめ想像され、ドラマチックに仕立てられ、